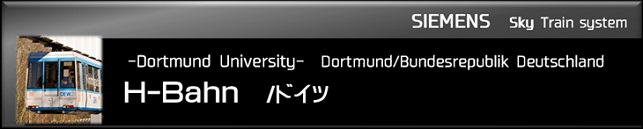
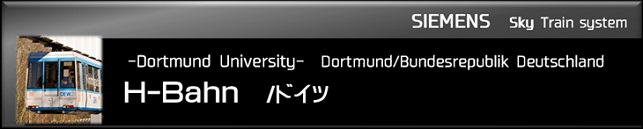
- H-バーン-(ドルトムント工科大学)
Dortmund_H-Bahn-

(c)PiLensPhoto- stock.adobe.com
1.H-Bahn(ドルトムント工科大学)ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州の都市ドルトムントには、ドルトムント工科大学(Technische Universität Dortmund、略称TUドルトムント)の南北キャンパスおよび周辺地域を結ぶ懸垂式モノレール「H-バーン(Hängebahnの略)」が運行されている。1984年5月2日に開業した本路線は、当初は全長約1.05キロメートル、大学の北キャンパスと南キャンパスをつなぐ比較的短い路線としてスタートした。その後、技術パーク方面へ延伸され、現在の総延長は約3.162キロメートルとなっている。
1993年には、アイヒリングホーフェン方面とSバーン駅とを結ぶ約900メートルの分岐線が開業し、大学と都市鉄道網との連携が強化された。2003年にはさらにテクノロジーパーク駅まで約1.2キロメートルの延伸が行われ、研究施設や技術系企業エリアとのアクセスも向上した。こうした拡張は、大学を中心とした産学連携や研究クラスター形成の一助ともなっている。 1号線:テクノロギーパーク-ドルトムント大学-南キャンパス-アイヒリンクホーフェン 2号線:北キャンパス-南キャンパス
H-バーンの最大の特徴は、無人自動運転が実現されている点にある。中央制御室が走行を一括管理しており、車両には運転士が乗務しない。運転方式は、あらかじめ決められたダイヤによる“定時運行”と、閑散時間帯に乗客がボタン操作などで車両を呼び出す“呼び出し運行”の二種類が併用されている。これに加えて、1990年代の改修により車両位置の検出精度が向上し、列車同士の間隔を短縮しながらも安全性を確保できるようになった。これによりピーク時の輸送力も改善されている。
車両はボックスガーダー(中空箱桁)と呼ばれる軌道構造に懸垂され、ボックス桁内部に収められたゴムタイヤで走行する。車体は片側のホームドアと連動し、安全性に配慮された設計となっている。走行音は比較的静かで、一部区間では約16メートルの高さを走行し、歩行者や既設道路との干渉を最小限に抑えている。支柱間の最大スパンは約38.5メートルとされ、道路や自然保護区を跨ぐ際にも有効な構造である。 2.シーメンス「SIPEM」H-バーンの母体となっている技術方式は、ドイツのシーメンス社が開発した懸垂式モノレール「SIPEM(Siemens People Mover)」である。SAFEGE方式に分類される懸垂モノレールの一種で、1970年代から研究開発が進められた。SIPEMは中央制御による無人運転や、モジュール化された分岐器構造など、都市内の限られた空間でも成立しやすい設計思想を持っている。特に大量輸送までの能力は必要ないが、一定の利用者を効率的に輸送したい環境に適していると評価されている。一方で、この方式が広く普及しなかった理由として、導入コストと費用対効果、メーカー側の販売戦略転換などが挙げられる。実際、ドルトムントでも2000年代後半以降、さらなる延伸案が検討されたものの、採算性の観点から実現に至らなかった例がある。ただし近年になり、延伸の経済的合理性を肯定する調査も登場しており、将来の拡張計画が再び浮上する可能性も残されている。 現在のH-バーンは、年間でおよそ160万人が利用するとされ、大学キャンパス交通として高い稼働率と信頼性を維持している。キャンパス間移動の効率化は、学生・教職員の利便性向上に寄与し、大学自体の機能統合にも影響している。また、技術パーク方面へのアクセス向上は地域産業との連携を象徴し、“実証型の高度交通システム”として都市モビリティ政策の一例と評価されている。 懸垂式モノレールは、地上スペースが限られた施設や用途向けに強みを持つ。H-バーンは、その導入事例として数少ない成功例のひとつであり、都市のコンパクト化や自動運転技術の発展を示す象徴的な存在と言える。今後、新たなニーズの高まりとともに、追加の延伸や更新計画が再び注目される可能性もあるだろう。 3.H-バーンが用いるSIPEM方式と、SAFEGE方式の比較懸垂式モノレール技術であるSAFEGE方式は、1950年代にフランスで開発された構造形式で、箱型の軌道桁の内部に走行輪や案内輪を配置し、その下面に設けられたスリットから車体を吊り下げる構造が特徴であった。この方式は地上占有が少なく、曲線や勾配に強いことから都市交通の未来形として期待されたが、商用化例は限られ、世界的には実用化の進展は限定的で、代表例として日本の湘南モノレールが挙げられる。一方で、この方式は当時の技術水準により、分岐機構が複雑かつ大規模になりがちで、保守性も十分に考慮されていなかったため、黎明期の実証色が強い方式となった。これに対して、ドイツのシーメンス社が1970年代に開発したSIPEM方式は、SAFEGE方式と同様に懸垂式構造を採用しつつも、都市や施設の内部交通としての実用性を重視して改良された発展型に位置づけられる。SIPEM方式では、ボックスガーダー内部にゴムタイヤ式走行輪と案内輪を配置し、車体を下方に懸架する基本構造を維持しながら、無人自動運転や遠隔監視、通信システムとの統合といった機能が設計段階から考慮されている。これにより、制御システムの統合度が向上し、列車間隔の短縮や運行効率の向上、安全性の確保が実現された。また、分岐器の仕組みも改良され、短い案内板によって車両の案内輪を誘導する方式が採用され、設置性や保守性が大きく改善されている。
さらに、ホームドアとの親和性も高く、乗降時の安全性が向上している点もSIPEM方式特有の特徴である。SAFEGEが後付け安全策で対応していたのに対し、SIPEMでは統合設計として組み込まれているため、近代的安全規格に適応しやすい構造となっている。保守性の面でも、内部へのアクセス性が改善され、部品の標準化が進むことで、運用コスト全体が軽減されるよう配慮されている。これらの要素の結果として、SIPEM方式は空港や大学キャンパスなど、中容量輸送が求められる空間で特に高い適性を示している。 商用展開という観点から見ると、SAFEGE方式は革新的な技術であったにもかかわらず、実用例はごく限られ、後期には保守性や規格適合性の課題が浮上した。一方、SIPEM方式は導入例自体は多くないものの、大学や空港といった限定された領域で安定プラットフォームとして運用されており、その成功例としてドルトムント工科大学のH-バーンが挙げられる。もっとも、メーカー側の販売戦略縮小により普及が広がらなかったという背景も無視できない。 技術思想の観点では、SAFEGE方式が「都市空間制限の克服」を中心に据えた研究的性格が強いのに対し、SIPEM方式は「既存交通網の補完として成立する実用交通システム」という方向性を明確に持つ。つまり、SAFEGEが懸垂式モノレールの基礎技術としての位置づけであるのに対し、SIPEMはそれを現実空間に適応させるための改良技術であり、制御系統や安全規格、保守体系を含めた総合交通システムとして成熟した方式といえる。 総じて、SAFEGE方式は技術的・構造的革新をもたらし、その後の懸垂式モノレールの設計思想に大きな影響を与えた。一方、SIPEM方式はその欠点を補いながら発展的に応用され、無人運転や統合制御、安全性の向上など、現代の都市交通が求める要素を多数取り込んだ形式である。ドルトムントのH-バーンは、その代表的成功例として運用されており、限られた都市空間における効率的な中容量交通手段として高く評価されている。このように、SAFEGE方式とSIPEM方式は技術的連続性を持ちながらも、それぞれ異なる歴史的背景と実用上の目的を備え、懸垂式モノレール技術史において重要な位置を占めている。
|
||||||||||
|