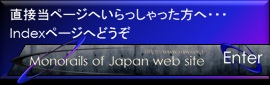 ※新しいウィンドウが開きます。
※新しいウィンドウが開きます。![]()
跨座型モノレール-アルウェーグ(ALWEG)式モノレール
| 2.アルウェーグ(ALWEG)式モノレール 現在のモノレールの原点であり、主流となっている方式がこのアルウェーグ式です。国内の主要路線である犬山遊園モノレール線(日立ALWEG)、東京モノレール(日立ALWEG)、奈良ドリームランドモノレール(東芝式)、横浜ドリームランドモノレール(東芝式)、北九州モノレール(日本跨座式)、大阪モノレール(日本跨座式)、多摩モノレール(日本跨座式)、沖縄モノレール(日本跨座式)をはじめ、海外でも重慶軌道交通(中国:日本跨座式)、クアラルンプールモノレール(マレーシア:Scomi)、ムンバイモノレール(インド:Scomi)、サンパウロ地下鉄(ブラジル:Bombardier)などの新規建設路線がこの方式から派生しています。 アルウェーグ式は、それまでの跨座式モノレールと大きく異なり、ゴムタイヤを走行用および案内安定輪に使用しました。この設計により、走行の安定性が向上し、静粛性や乗り心地も大幅に改善されました。これが、アルウェーグ式が主流となった大きな要因です。
上の写真に示すモノレール台車では、軌道桁に対して上面で接する4個の走行タイヤにより上下方向の荷重を支持しています。これにより、車両の重量が安定して軌道に伝わります。また、軌道桁の側面に接する4個の案内タイヤと2個の安定タイヤにより、水平方向の案内および支持を行う構造となっています。 この構造により、モノレール車両は前後左右に安定して走行でき、カーブや勾配のある軌道でもスムーズな運行が可能となります。具体的には、走行タイヤが車両の重量を支える一方、案内タイヤが車両の横方向の動きを制御し、安定タイヤが揺れを抑制する役割を果たしています。この複合的なタイヤ配置により、モノレールは静かで安定した乗り心地を提供できるのです。 さらに、ゴムタイヤの使用により、騒音が少なく、地上の交通や住民への影響を最小限に抑えることができます。この設計は、都市部での運行に非常に適しており、モノレールが高架上を走行する際の優れた静粛性と安定性を実現しています。
2-1.アルウェーグ(ALWEG)式の幕開け スウェーデンの産業経営学者アクセル・レナート・ウェナーグレンは、第二次世界大戦後にモノレールの開発事業を開始しました。「アルウェーグ (ALWEG)」という名称は、創設者である彼の名前の頭文字から取られています。ウェナーグレンは西ドイツのケルン市郊外「Fuehlingen」に1/2.5スケールの楕円形のモノレール試験線を設置しました。ここでのテスト車両は、最高速度160km/hを達成しました。このデータを基に、1957年7月には実用スケールでのモノレールシステムを試験しました。 これらのシステムは、ディズニーランド内の移動設備を模索していたウォルト・ディズニーの目に留まりました。1958年にウォルト・ディズニーとアルウェーグ開発は共同でディズニーランド導入用のモノレールを試作し、翌1959年には5/8スケールのディズニーランドモノレールが実現しました。このモノレールは、ディズニーランドの魅力を大いに高めるとともに、アルウェーグ方式の優れた実用性を世界に示すこととなりました。 その後、アルウェーグ式モノレールの技術はさらに進化を続けました。ボンバルディア(カナダに本社を置き、ボンバルディアトランスポートはドイツに拠点を持つ)は、この技術を元にMark IVへと進化させました。日本では日立製作所がアルウェーグ技術を取り入れ、その後、スコミ・レールへと派生していきました。現在では、アルウェーグ式モノレールシステムは世界的に広がりを見せています。 近年ではCRRC(中国中車)等を中心に、中国でも大きく路線長を伸ばすアルウェーグ式モノレール。CRRC(中国中車)は、中国の大手車両製造会社であり、国内外で多くのモノレールプロジェクトを手掛けています。CRRCは、中国での製造パートナーとして、アルストムとの共同事業(合弁会社)を通じてINNOVIA Monorail 300の製造および保守を担当しています。INNOVIA Monorail 300は元々ボンバルディア・トランスポーテーション(Bombardier Transportation)によって開発されました。アルストム(Alstom)は2021年にボンバルディア・トランスポーテーションを買収し、この技術を引き継ぎました。CRRCとアルストムの協力により、INNOVIA Monorail 300は中国および世界各地で成功を収めています。 アルウェーグ式モノレールの具体的な導入例としては、ラスベガスモノレールの延伸やブラジル・サンパウロ地下鉄への導入があります。ラスベガスモノレールは、観光客の主要な移動手段として利用されており、その利便性と効率性が高く評価されています。ブラジルのサンパウロ地下鉄でも、都市交通の一環としてアルウェーグ式モノレールが建設され、都市の交通問題解決に寄与しています。  写真 フロリダ ディズニーリゾート モノレール(MarkⅣ) ディズニーランドでの成功後も、モノレールは遊園地や博覧会用として次々と小規模な路線が建設されました。1961年にはイタリアのトリノで開催された博覧会で運行され、続いて1962年にはシアトルで開催された21世紀万博(シアトル万博)で運行されました。 日本国内では、日立製作所が最初に技術導入を行い、1962年には犬山遊園モノレール線(ラインパーク)を開設しました。さらに、1963年には読売ランド(関東レースクラブ)、1964年には東京モノレールが開通し、本格的な営業路線としてのモノレールの普及が進みました。 これらのプロジェクトにより、モノレール技術は日本国内での実用的な交通手段としての地位を確立し、その後の都市交通インフラの重要な一部となっていきました。  写真 日立アルウェーグ(ゆいレール展示館/那覇) 2-2.日本跨座式 1967年、当時国内で渋滞問題が悪化する一方で、より優れた輸送手段としてモノレールが注目されました。時の運輸省(現国土交通省)は、日本モノレール協会※に「都市交通に適したモノレールの開発研究」を委託しました。 その結果、日本版アルウェーグ(ALWEG)として、日本跨座式モノレールが誕生しました。日本跨座式はアルウェーグ式をベースにしており、軌道桁を太くし、2軸ボギー台車を採用しました。国内導入時のアルウェーグ式(犬山遊園線や東京モノレールなど)に対し、走行輪の直径を小さくし、幅を広くすることで、床面の高さを高く保ち、室内へのタイヤハウスの出っ張りを無くしました。 しかし、その反面、重心が高くなることにより、曲線通過速度が遅くなるというデメリットが発生しました。また、トンネル建設の際のコストが大きくなるという課題もありました。 ※日本モノレール協会とは:日本モノレール協会は、1964年8月10日に設立された一般社団法人です。協会の主な目的は、モノレールの技術的発展と普及を図り、新しい交通機関としてのモノレールの可能性を追求することです。これにより、都市交通の効率化や渋滞問題の解決に寄与することを目指しています。
東芝式モノレールは、ALWEG式モノレールを参考にしつつ、すべて国産技術によって完成した初のモノレールです。これは、日本の技術力を結集した結果であり、その設計と製造には多くの革新的な要素が取り入れられました。
もともとマレーシアでは、日立製作所主導によるモノレール計画および建設が進められていました。しかし、1997年のアジア通貨危機の影響を受け、同計画は中断を余儀なくされました。 翌年の1998年、マレーシア国内でこの計画を再始動させるため、国内企業であるMTrans(当時の名称)がプロジェクトを引き継ぎました。国内メーカー製の車両を使用することでコスト削減を図り、計画の再開を目指しました。これが、マレーシア産(スコミ製)モノレールの始まりでもあります。数年が経過し、2003年8月にマレーシア国産のモノレール路線であるKLモノレール(全長8.6km)が開業しました。 Scomi Railは、2007年にMTransを買収して誕生し、以降、モノレールの設計・製造に注力してきました。特に、Scomi Urban Transit Rail Application(SUTRA)というモノレールシステムが開発され、これが同社の主要製品となりました その後もスコミは国外での受注を増やし、2014年にはムンバイにインド初のモノレール路線を開業させています。さらに、ブラジルでのモノレール計画も複数受注しており、同システムを世界中に広めつつありました。しかし、Scomi Railは2019年に財務問題に直面し、受注したサンパウロのモノレールプロジェクトで契約が解除されるなど、いくつかの困難に見舞われました。その結果、Scomi Railは経営再建手続きを開始し、現在はモノレールシステムの販売を行っていません。
〔開業・一部開業路線〕 2003年 KLモノレール(マレーシア) 2014年 ムンバイ・モノレール(インド)一部開業8.26km(総延長20km) 〔計画路線〕 2004年 プトラジャヤ・モノレール(マレーシア・中断)) 201X年 サンパウロメトロ・17号線(ブラジル)21.5km 201X年 サンパウロメトロ・18号線(ブラジル)15km 20XX年 マナウス・モノレール(ブラジル)20km 2-6.CRRC(中国中車) CRRCとは中国中車の略称であり、中国の国営企業です。2014年に中国北車と中国南車が合併し、世界最大規模の鉄道車両メーカーとなりました。その事業規模は、鉄道ビッグスリーと呼ばれるボンバルディア、アルストム、シーメンスの鉄道部門の売上合計を遙かに凌ぐと言われています。 2016年5月19日、CRRC四方社は駆動機構に永久磁石同期電動機を配した跨座型モノレールの試験を実施しました。試験は青島(Qingdao:山東省)にあるCRRC四方社の構内で行われました。モノレールの開発は2013年に開始され、その開発の95%を中国国内で行っています。 同社は2016年を中国産モノレールの展開元年と位置づけており、今後世界規模でモノレールシステムを輸出するモノレールマニュファクチャラーとなっていきます。 2-7.BYD 中国、深センに本社を置く自動車および電池メーカーであるBYD 社。 2016年10月13日、BYD社は本社内に設置したおよそ4.4kmのテストコースで同社初のモノレールシステムの発表会を実施しました。 モノレールシステムの名称は「Skyrail:スカイレール」。 スカイレールは、プロジェクト期間5年、50億元を掛けて開発。 今後、中国国内の中小都市のみならず、観光スポットや中心業務地区への導入を目指しています。 同社広報によれば、スカイレールは時間あたり(方向)最大30000人の乗客輸送能力を備え、最高時速は80km/hとしています。 スカイレールの初導入路線は、今後250kmのネットワークが計画される広東省、汕頭となっています。 2-8.モノレールマニュファクチャラー(アルウェーグ式) 現在、アルウェーグ式モノレールを巡るマニュファクチャラー情勢は、新しい時代に突入しつつあります。ALWEGの開発から始まり、ディズニーランドモノレールの成功を経て発展を続けるボンバルディア社、日本が誇る日立製作所による日本跨座式、そして残念ながら撤退したものの、時代が生んだ新星であるマレーシアのスコミレール(旧MTrans)、CRRC。これらの企業が競い合う中、今後もモノレールメーカー各社による海外展開が激化することが予想されます。
|
|||||||||||
|
スポンサーリンク
スポンサーリンク |