
Welcome to mjws!The index page is here.
![]()


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.国内各社工作・作業車保有台数 国内におけるモノレール事業者の工作車保有台数は、営業延長や開業からの経年による施設の老朽化進行に伴い、増加傾向を示している。特に東京モノレールにおいては、経年劣化および補修対象箇所の増加に加え、海上橋梁部および地下構造区間の存在により、それぞれの構造特性に応じた専用保守用車両の配備が求められた結果、他事業者に比して保有台数が多くなっている。 動力方式に着目すると、東京モノレールではDE形に代表される内燃機関搭載型の工作車が主流を占めているのに対し、1985年開業の北九州モノレール以降に開業した各社では、主としてバッテリー電動式の工作車が導入されている。この傾向は、都市モノレール法施行後に都市部へのモノレール整備が進展し、深夜帯における保守作業時の騒音低減が社会的要請となったことが背景にある。 もっとも、機関性能の観点からは、依然として内燃機関式が優位であり、最高運転速度は通常型で約60km/h(牽引専用型では約40km/h)に達する一方、バッテリー式車両ではおおよそ30km/h程度にとどまるのが実情である。これにより、作業内容や運用環境に応じて、動力方式の選定には一定のトレードオフが存在している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.モノレール運営会社毎の工作車(保線車)
北九州高速鉄道(北九州モノレール)の工作車
![]()















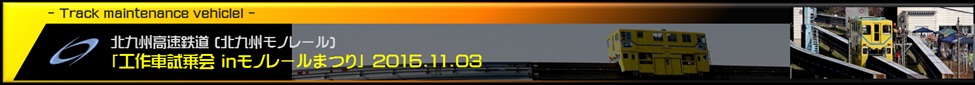


各事業所の保守車両
![]()


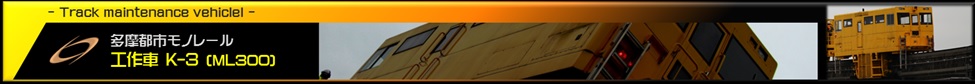

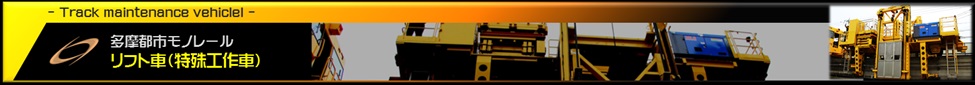

![]()





![]()

![]()

![]()





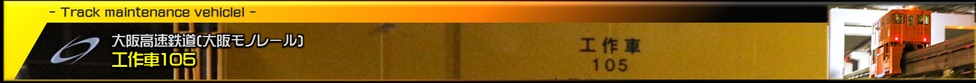



![]()
| 5.工作車(保線車) 海外マニュファクチャラーおよび保線車両 | |
L&S GmbH MIV 1-25 (c)L&S GmbH 2011 MIV 1-25 サンパウロメトロ15号向け保線車両 (サンパウロメトロ17号線で使用) |
Intamin Transportation Ltd. (c) Intamin Transportation Ltd. P8およびP30モノレールシステム向けメンテナンス車両 牽引、救助、清掃、およびメンテナンス用のメンテナンスおよびレスキュー車両の役割を果たす。 |
Hubei Srida Heavy-duty Engineering Machinery Co., Ltd (c)Hubei Srida Heavy-duty Engineering Machinery Co.、Ltd SRK-200 モノレール保線車両(重慶モノレールで採用) |
 重慶軌道交通2号線 バッテリー工作車 |
 重慶軌道交通2号線 工作車B16 |
 重慶軌道交通2号線 工作車B16(側面) |
 重慶軌道交通3号線 C26工作車 |
 重慶軌道交通3号線 C28工作車 |
 重慶軌道交通3号線 軌道モーターカー |
 重慶軌道交通2号線 クレーン工作車 |
 タイ イエローライン (c)shutterstock |
 エジプトカイロ 新行政首都線 (c)shutterstock |
 (c)Cyclosystem Pte Ltd Railway Maintenance Vehicles (セントーサエキスプレスで採用) |
 西安 /中国 インタミン式モノレール保線車両 |
 エジプトカイロ 新行政首都線 ケーブル敷設作業台車 (c)shutterstock |
|
| 6.その他特殊工事車両(海外) | |
 サンパウロメトロ向けホイスト工事車両 (c)Adbee |
 エジプト新行政首都線工事車両(陸送移動中) |
 バンコクイエローライン (c)shutterstock |
 バンコクイエローライン (c)shutterstock |
5.工作車(保線車) 保守作業アルバム(保守作業の様子) |
夜間保守作業 は撮影日毎にUPしております。下記リストより選択下さい。
![]()
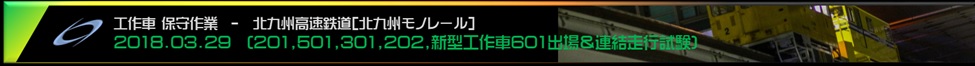
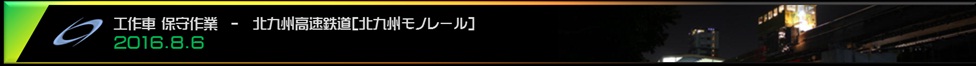
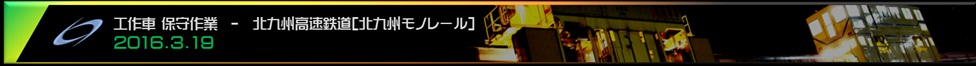
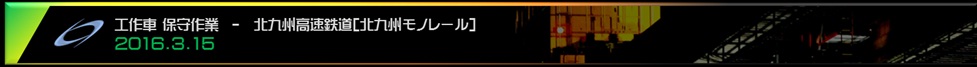
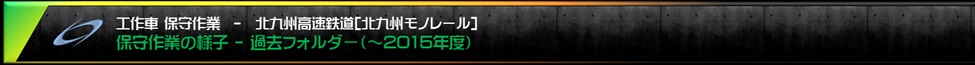
私達乗客の安全を日々守ってくれている保線車両、それが工作車
今日も日々の安全を絶やさないため、彼らは静かな夜に走り出します。
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
|
|||||||